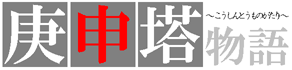
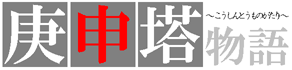
宇佐八幡宮が所蔵する『庚申因縁記』には「其日ノ精進ニテ可待一座ト云ハ、三年ニ十八度有也、 十八度ヲ一度モ解怠ナク守ヲ一座ト云也、此ノ一座ヲ守レバ、一切ノ願望、此内ニ成就セスト云事ナシ」と三年一座、 つまり3年間に18度の庚申待を行うことを説いている。
多摩地方にも三年一座を記した次のような塔がある。 [表1]参照
| No. | 年銘 | 西暦 | 中尊 | 塔形 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正徳2年 | 1712 | 青面金剛 | 柱状型 | あきる野市上代継真城寺 | 合掌6手 |
| 2 | 宝暦11年 | 1761 | -- | 宝篋印 | 日野市下田 八幡神社 | 三六度 |
| 3 | 文化6年 | 1809 | 青面金剛 | 笠付型 | 八王子市東中野 | 合掌6手 |
1の正徳2年塔は、刻像塔で「庚申尊像三箇年日待成就二世安楽所」の銘文がみられる。 「三箇年日待」は、3年間にわたった日待、つまり庚申待を続けた意味であり、「三年一座」を現している。
2の宝暦11年宝篋印塔に長い銘文が4面に刻まれているが、その中に「青面金剛三六度待」がみられる。 青面金剛を「三六度待」とは3×6度の庚申待を意味し、つまり「三年一座」を示した銘文である。
3の文化6塔は合掌6手の青面金剛刻像塔で「奉待六夜三年」の銘が刻まれている。 この銘文は、1年6回の庚申待を3年続けたことを物語っている。